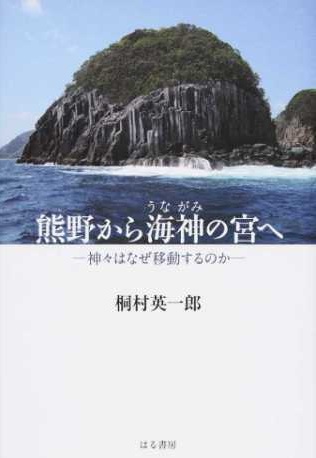5月22日、日本記者クラブで行われた日大アメフト部選手の記者会見に出ました。関西学院との定期戦で、相手のQBに対して反則行為を行ったとして退場処分になった選手です。本人が話す前に、代理人の弁護士から、顔も名前も報道されてもいい、という申し出が本人からあったとの説明がありました。会見は相手選手に対する謝罪の一環なので、顔も名前を隠していては、謝罪にならない、という理由だったそうです。潔い態度に感心する一方で、「アメフトを続けていく権利はないと思っていますし、この先アメフトをやるつもりはありません」と語るまでに、選手を追い詰めた日大の監督やコーチなどスタッフの「体質」に怒りと悲しみを覚えました。
この選手が読み上げた「陳述書」を読み直してみると、相手のQBをつぶしてこい、という内田正人監督・井上奨コーチの指示は、事前に仕組まれていたのではないかという疑問が浮かんできました。
定期戦が行われたのは5月6日ですが、その3日前の練習で、監督・コーチから「やる気が足りない」という指摘を受けて、翌日(試合の2日前)には監督から、すでに日本代表として選抜されていた大学世界選手権に大会を辞退するように言われ、実戦練習も外されたそうです。さらに、試合前日には、実戦練習からはずされ、コーチからは、次のように言われたとあります。
「監督に、お前をどうしたら試合に出せるか聞いたら、相手のQBを1プレー目に潰せば出してやると言われた。『QBを潰しに行くんで僕を使ってください』と監督に言いに行け」
そして試合当日、試合のメンバー表に自分の名前がなかったので、監督に「相手のQBを潰しに行くんで使ってください」と伝えたところ、「やらなきゃ意味ないよ」と言われ、試合前の整列時には、コーチが近づいてきて「できませんでしたじゃ、すまされないぞ。わかっているな」と念を押された、とあります。
ヤクザの戦争では、相手のトップを狙うヒットマンを「鉄砲玉」と言うそうですが、監督・コーチのなかで、まさに鉄砲玉をだれにするか事前に相談したうえで、この選手に日本代表の辞退やスタメンはずしで退路を断たせて、反則行為に追い込んだように思えるのです。
会見場に選手が現れたときに、高校野球の選手のようだと感じました。選手の説明を聞いていて、その理由がわかりました。試合の前日、井上コーチから「関学との定期戦が無くなってもいいだろう」「相手のQBが怪我をして秋の試合に出られなかったらこっちの得だろう」などと言われたうえ、髪形を坊主にしてこいと指示されたというのです。スポーツマンシップに反する反則行為をさせるためのパワーハラスメントと言うしかありません。
試合後、監督は、スタメンと4年生の選手を集めて、「こいつのは自分がやらせた。こいつが成長してくれるならそれでいい。相手のことを考える必要はない」と言ったそうですが、その後、関学から抗議が起きると、「指導者による指導と選手の受け取り方に乖離が起きていたことが問題の本質」(日大アメフト部から関学アメフト部への回答書)として、選手の反則行為は監督・コーチの指示を誤解しただけだと切り捨ててしまいました。この日の会見後にも、日大は同様のコメントを出しました。
今回の事件の「本質」は、監督と選手との意思疎通の乖離ではなく、勝つためには手段を選ばないという「勝利至上主義」にあるのは明らかです。そして、勝利のためには、選手を犠牲にすることもいとわないのですから、この勝利の栄光は、選手ではなく、部という組織であり、それを代表する監督にあるのも明らかでしょう。
大学の部活動は、本来は部員の主体的なスポーツ活動で、それを助けるのが監督やコーチの役割だと思います。高校までの部活動は教育の一環ですから、位置づけは違うと思います。しかし、部活動を通じての人間形成は、中学・高校も大学も同じはずですが、日大のアメフト部は、どんな卑劣な手段を使ってでも勝てというのですから、人間形成の場とは、とてもいえません。
内田監督は、監督辞任を表明したときに、日大の常務理事については、「関係ない」として、続ける意向を示したようですが、内田監督の権力の源泉は、常務理事として、さまざまな権限を持っていることですから、監督を辞めても、内田体制が変わることはないでしょう。どこまで監督の指示を受けているのかわかりませんが、監督の意を汲んで、具体的な指示を出していたコーチの言葉を陳述書で読めば、その感を強くします。
今回の事件は、関学が問題視して、抗議という行動を起こしたことで、社会問題になりましたが、こうしたゆがんだ勝利至上主義は、日本の学校スポーツに蔓延しているように思えます。優秀な成績をあげれば、学校の宣伝になり、監督の名声も高まるので、監督は選手の人間形成や健康は犠牲にしても、勝利をめざすというのは、多くの学校にあてはまる現象に思えます。「わが内なる日大アメフト部」という反省は、どこであろうと部活の指導者には実践していただきたいことです。
それにしても、トップの指示がどこまであったのかわかりませんが、部下が不適正な行為をしでかし、それが明るみに出ると、トップは知らん顔という構図は、いまや日本の定番になってきましたね。